『フォードvsフェラーリ』感想
これは車に興味ない人にも是非観て欲しいって思えるほど名作だった…
ケンの奥さんが、ケンが本心を隠している事に腹を立ててあえて危険な運転するところの気性の荒さとか、ケンとシェルビーの喧嘩のくだりでシェルビーが加減して飲み物の缶ではなくお菓子の袋を持ってケンを殴ったりするところとか心情描写がとても細やか。
他にもフォードの役員が買収のためにフェラーリを視察する時の「マフィアが自由の女神を買いに行くようなもの」「どちらがマフィアか分からない」といったくすぐられる台詞回し等素直に楽しめる要素が多かった。
そのうえで、えぐり出し投げかけているテーマは素直に受け止めにくいところが絶妙だったのが本作だと思う。
「7000回転の世界」の詩が示す『アメリカ人とは何者か』という問いが全体に蔓延していて、それは挑戦者としてのシェルビーとケンにまつわるものではあったし、先代が「開拓」した道筋を受け継いだ2代目フォード社長にもかかってると思った。
当初そのモチーフは「挑戦を諦めないアメリカ人の開拓精神」って形でかかってくるものだと思っていたのだけど、結末を見るとその印象がガラッと変わってくる。企業体としてのフォードからは既に開拓者精神は失われたという強烈な批判が、イギリス人であるケンとの対比でより強く浮き彫りにされた印象を受けた。
響け!ユーフォニアム 8話由来のアイコン
山登り/階段上り


靴による対比















幾原邦彦講座(朝日カルチャーセンター新宿) メモその2
幾原邦彦講座(朝日カルチャーセンター新宿) メモ
甲鉄城のカバネリ1話 二度見ピックアップ





作画ファンとしてのピックアップ
この後のけん玉を振り回すシーンも面白いのですが個人的にはここが印象に残りました。
 (この画像は既に動いた後になります)正面を向いている状態から馬を操り後ろへ向き直ります。この時馬の動きが先にあり、それに遅れて上体が少し反ってからこの画像のような体制をとります。ここもしっかり慣性を感じる写実的な動きが成立していて上手いです。
(この画像は既に動いた後になります)正面を向いている状態から馬を操り後ろへ向き直ります。この時馬の動きが先にあり、それに遅れて上体が少し反ってからこの画像のような体制をとります。ここもしっかり慣性を感じる写実的な動きが成立していて上手いです。1話で満足した人へ、少なくとも3話まではこのクオリティの作品が続くので楽しみにしてください。
*1:これは特効と呼ばれる処理によるところらしいです。役職名は『メイクアップアニメーター』とクレジットされているのだとか。
主人公は『みらい』でなく『りこ』? 魔法使いプリキュアテーマ推察





GO!プリンセスプリキュア テーマ考察
なぜプリンセスなのか?
そもそも"プリンセス"とはどういった意味か、なぜこの言葉は作品の中心的な部分に象徴として描かれているのか。私はプリンセスの「フィクションの中にのみ存在し、現実には存在しない」という性質に注目した。

はるかの憧れの存在である"花のプリンセスは"同名の絵本の主人公である。彼女はフィクションの中の主人公として特別な地位にいる。しかしながらプリンセスプリキュア内の実社会には(トワという『異世界でお姫様』という例外もあるが)プリンセスが存在するような事はない。これは本作の舞台が"花のプリンセス"の世界より"私達の現実の世界"に近い事に起因している。
これにより"プリンセス"という言葉がプリキュア達を絵本(=フィクション)の中にのみ許された存在だという印象を強め、彼女らの人間性に「まるで物語の主人公のような存在」という印象を付与するように機能している。
プリキュアは魔法の力によって、戦うプリンセスへと一時的な変身を遂げる。
この瞬間彼女達は「この物語の主人公である」事をより強く象徴化されているのだ。この事をまず定義してから次のテーマについても語りたい。
七瀬ゆいの存在
プリンセスプリキュア48話にて、プリキュア達の正体が一般人にばれてしまう。これにより一般人にとって自分達の身近な存在が、(魔法による変身という一時的なものではあるが)プリンセスという「物語の主人公の様に特別な存在」だった事が明かされる。
今まで夢を見る事の大切さを説いてきたプリキュア達だが、実は彼女らは一般人にとっての日常側に属する人物であり、その言葉に説得力を与えている。
しかし彼女達の正体が明かされるという工程が「変身が解かれることによって」ではなく、「その逆」である事により一般人にとっては驚きが優先され、前述したテーマを表現するためのシナリオを挿入しにくい形となっている。
そんな状況で活躍するキャラクター、それが"七瀬ゆい"だ。彼女はプリキュアを一般人としての視点である「物語の主人公の姿」だけでなく「普通の女子中学生としての姿」も共に認識していた唯一の人物である。
彼女が絶望の檻を一早く抜け出す事が出来たのは主人公であるプリキュア達の姿に憧れを抱きつつも、その姿を決して遠ざけずにいて、そのため絶望をはねのける事が出来たからだと推察できる。そんな彼女は自分と同じように、その他の特別でない人々に希望を持つ事の大切さと普遍性を提示するのである。

メタフィクションの導入
【メタフィクションとは、第四隔壁の打破であり、フィクションがノンフィクションをフィクションに見立てる表現技法である。】(ニコニコ大百科より引用)
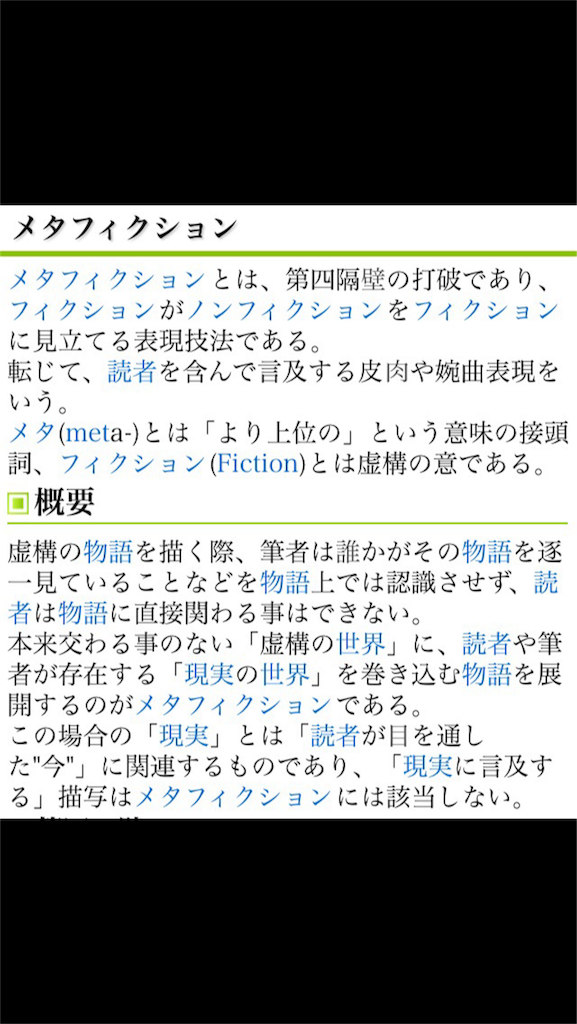
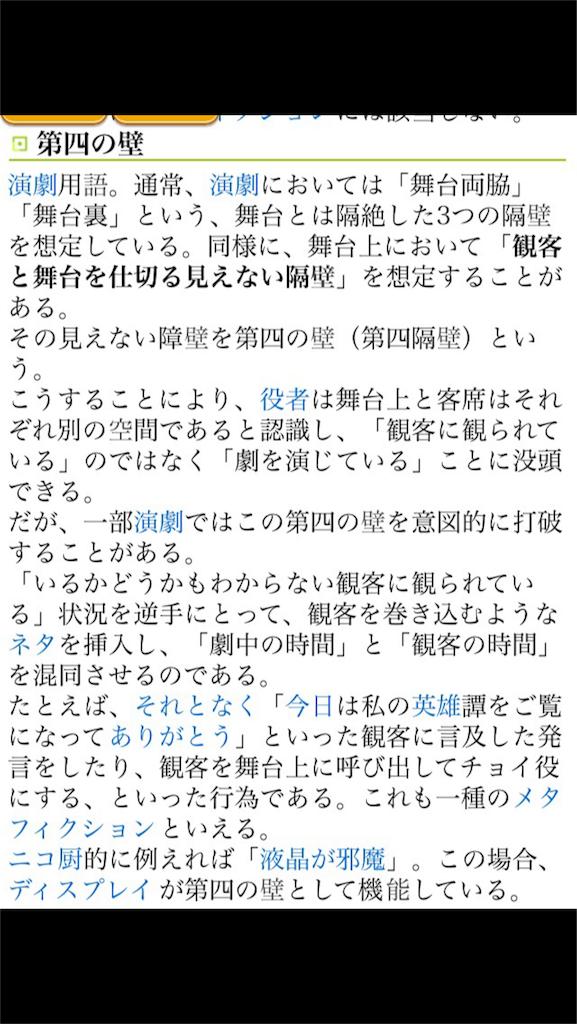
実はプリンセスプリキュアにもこの手法が用いられている。その目的は第四の壁(=観客と舞台を仕切る見えない壁)の打破である。
前述したように本作は作中に絵本が登場する。物語の中の別の階層にもう1つの物語を内包しているのだ。物語の"第1次階層"(プリンセスプリキュア)と、その中の"第2次階層"(作中のフィクション)という形で構成されているが、最終話のある描写によってこれが覆されている。
最終話のタイトル後、ある少女が「プリンセスと夢の鍵」という絵本を読んでいる。


この絵本はプリキュアの活躍をモチーフにした作中のフィクションである。本来は「プリキュアの活躍」という第1次階層で起きている物語が第2次階層に変換され読まれているという異質な事が成立している。何故このような事が起きているのか。
それはつまりこの少女が第1次階層より更に上の第0次階層のキャラクター(=現実世界の我々)であるという事の"暗喩表現"なのだろう。これによって第四の壁が破られ、伝えたいテーマが視聴者に向けて直接発信される。
最終回の大人はるかは私達に向けて希望を語る。この手法のおかげで「ただ在り来たりにいい雰囲気を作って終わり」ではなく、しっかりとテーマを捻出させる事に成功しているのだ。